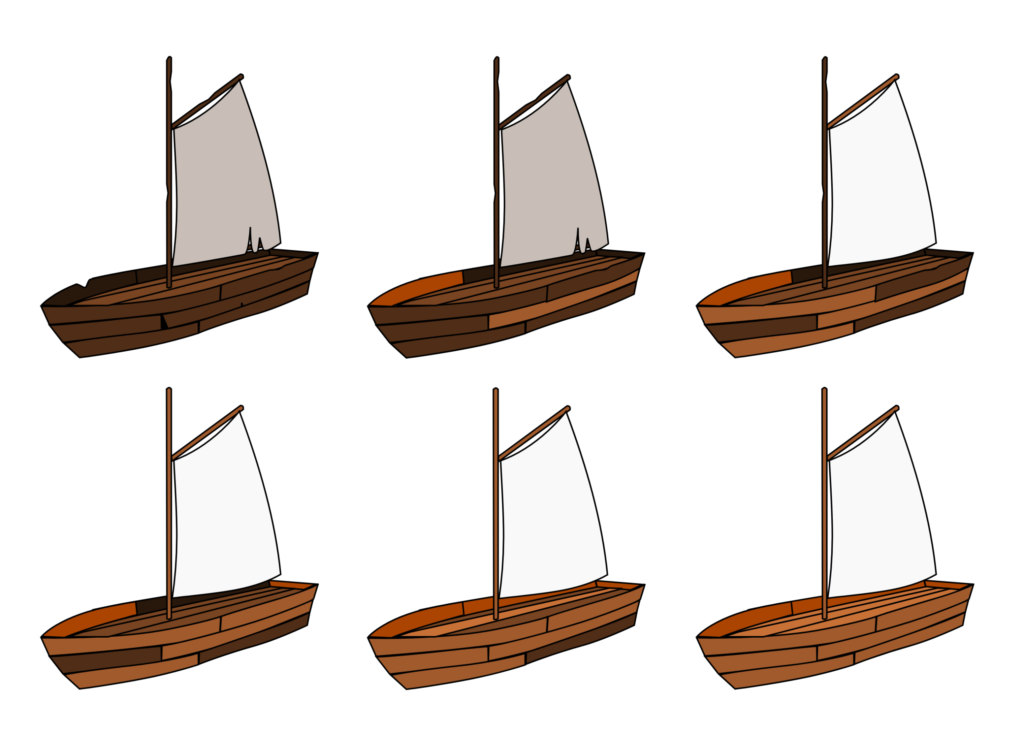―― 日常すぎて名前になれなかった食材 ――
夜の台北で牛肉麺をすすっていて、ふと疑問に引っかかった。
台湾には牛肉麺があるのに、豚肉麺という看板はほとんど見かけない。
豚は身近で、価格も安く、台湾の食卓では主役のはずなのに。
なぜだろう。
看板を眺めていると、
豚という文字は確かにそこら中にある。
ただ、単独で前に出てこない。
魯肉飯。排骨。控肉。肉燥。
豚は姿を変え、名前を変え、
料理名の一部として現れる。
それでも「豚肉麺」としては現れない。
ここに少しだけ、言葉の仕組みが見える。
しばらく考えてみると、これは単に料理の問題ではなく、
名前になる食材と名前になれない食材の話なのだと思えてくる。
豚は当たり前すぎて、名前になれない
台湾における豚肉は、あまりに日常的だ。
魯肉飯、排骨飯、担仔麺、乾拌麺、控肉飯、肉燥麺。
街の麺屋のほとんどが、何らかの形で豚肉を使っている。
言い換えると、豚肉はベースの味になってしまった。
マーケティングでいえば、カテゴリの土台に吸収されている状態だ。
ここで少しだけ、命名の視点が入る。
料理名は、材料の説明というより、差分の提示に近い。
「普通は入っていないもの」が入ると、
それは名前になる。
逆に「普通に入っているもの」は、
名前としては省略される。
台湾の麺にとって、豚は省略される側に回っている。
だから豚肉麺と名付けても、
何の情報も追加されない。
インパクトがない。
差別化ができない。
それ、全部の麺屋がやってるよねで終わってしまう。
名前とは本来、違いを伝えるための道具だ。
豚肉は便利すぎて汎用的になり、
逆に名前になる資格を失ったのだと思う。
豚の名前は「肉」や「燥」に溶けている
豚肉は、豚肉として前に出ない代わりに、
別の形で支配している。
肉燥。
肉羹。
滷。
排骨。
ここでは、豚は素材名ではなく、
加工された状態で呼ばれる。
素材の種類よりも、
調理法と質感が主語になる。
つまり、台湾では豚は「肉」で足りてしまう。
牛や羊のように、わざわざ指定する必要がない。
この省略の強さが、
豚肉麺という言葉を発生させない。
牛肉は、歴史的に特別な存在だった
対して、牛肉は長い間特別な食材だった。
台湾南部では農耕用の牛を食べることはタブー視され、
牛肉が広く食べられるようになったのは比較的近代になってからだ。
だからこそ、牛肉は珍しかった。
希少性があった。
そして、珍しいものには名前が付く。ブランドが生まれる。
牛肉麺は、その特別感を看板として押し出せる料理だった。
他の麺とは違う、牛肉入りを強く宣言できた。
豚では到達できない、
名乗った瞬間に差別化できる領域が、牛にはあった。
この差別化は、味だけではなく、
値段にも現れる。
牛肉麺は、屋台の麺の中では少し高い。
その「少し高い」が、看板の説得力になる。
牛肉麺という名前は、
内容の説明であると同時に、
価格帯の宣言でもある。
唐突に現れた牛肉麺ブランドの強さ
もうひとつ大きいのは、1949年以降の外省人文化だ。
中国・四川系の辛さと清燉(透明スープ)が混ざり、
戦後台湾の都市部で急速にブランド化した。
牛肉麺は、味だけでなく、ストーリーを持った料理として広がった。
軍人、外省人街、夜市、24時間営業。
物語を背負える料理は、強い。
牛肉麺は「名物」として語れる。
語られることで、さらに名物になる。
この循環がある。
一方、豚肉は物語を持たない。
便利で美味しいが、人生を背負っていない。
日常に溶けすぎている。
豚肉は、朝の飯にも、昼の弁当にも、夜の麺にもいる。
そこに特別な場面が発生しにくい。
ブランドは、日常の外側から来る。
牛肉麺が看板になり、豚肉麺が看板になれなかった理由は、
ここにもある。
名前にならなかったという凄さ
こうして見ていくと、豚肉麺が存在しない理由は単純だ。
豚肉が優秀すぎたからだ。
あまりに多くの料理に使われ、
日常の中心に入り込みすぎて、
専用の名前が不要になった。
マーケティング的にいえば、
豚肉はコモディティ化しすぎた。牛肉はブランド化した。
それだけのことなのだと思う。
ただ、街角の麺屋で、醤油と豚脂の匂いに包まれているとき、
名前が残らなかったという事実が、
逆に豚肉の豊かさを証明しているようにも感じる。
豚は、看板にはなれなかった。
その代わり、
台湾の食卓そのものになった。