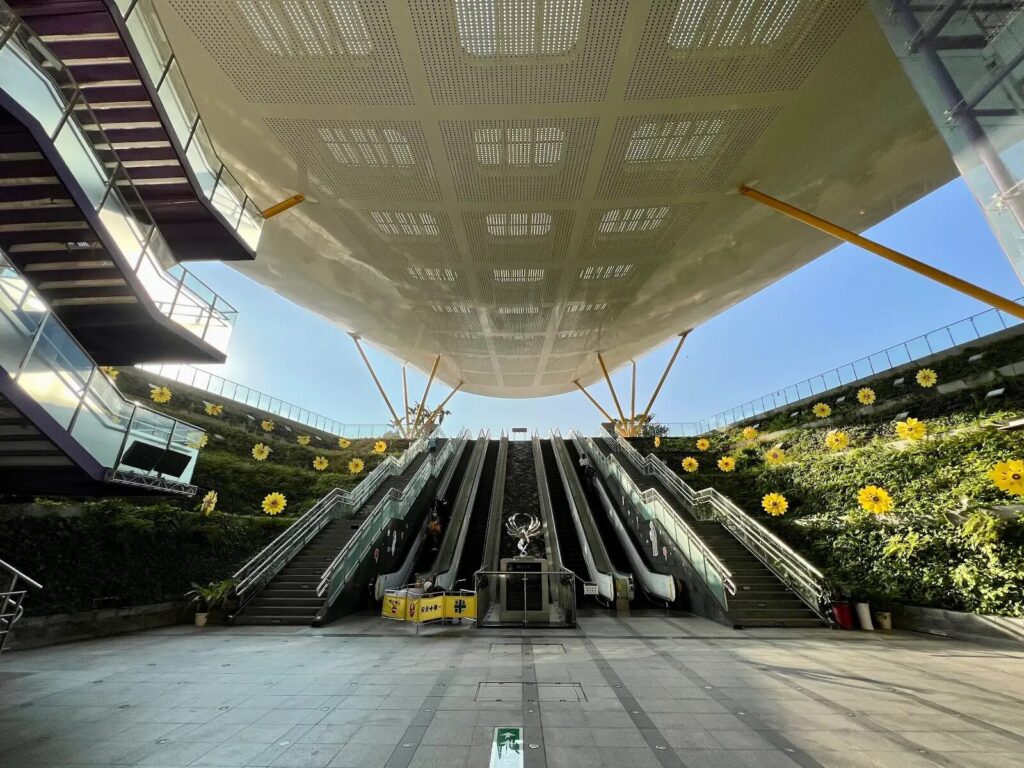―― 旅行者を惑わす、小麦と卵とネギ ――
台北や台中の朝食屋に入ると、壁のメニューに二つの似た言葉が並んでいる。
葱油餅と、蛋餅。
どちらも小麦粉が使われ、卵が入り、刻んだネギが散らされている。
見た目も名前も近いため、旅行者の多くはこれを同じ料理の別名だと受け取るように見える。
実際に鉄板の前に立つと、その混乱はさらに深まる。
薄い生地に卵を落とし、ネギを振り、ヘラで返す。
どちらの名前を指しているのかは、遠目には分かりにくい。
ただ、口に入れたときの印象には、ある種の断絶があるようにも感じられる。
歯が最初に当たる感触、噛んだときの戻り、油の抜け方。
それらは「少し違う」というより、異なる系統のものが並んでいるような違い方をしている。
練られるものと、流されるもの
この二つを味ではなく、構造として眺めると、差はよりはっきりする。
葱油餅は、小麦粉を水で練るところから始まる。
粉は塊になり、伸ばされ、油を塗られ、何度も折り畳まれる。
その過程で層が生まれ、重なり、再び押し広げられる。
デニッシュやパイのように、内部に空気の層を抱えた生地になる。
焼かれた後に残るのは、歯切れのある外側と、わずかに弾力を持つ内側である。
小麦のコシや油の香りが、ゆっくりと広がっていく。
蛋餅は、少し様子が異なる。
もともとは小麦粉を水で溶いた液体、いわゆる粉漿を鉄板に流す。
現在では、工場で作られた薄い皮を使う店も多い。
いずれにしても、そこには折り畳んで層を作る工程がない。
焼き上がった蛋餅は、均一な薄い膜のようである。
クレープやガレットに近く、具材を包むための皮として機能する。
しっとりとした口当たりは、葱油餅の層とは別の方向にある。
1949年と、その前から続く道
この構造の違いは、来歴の違いとも結びついているように見える。
葱油餅の旅は、比較的はっきりしている。
1949年以降、国民党軍とともに台湾へ渡った人々が、眷村で故郷の味を再現した。
寒冷地の小麦文化の中で育った、腹持ちのよい練り生地の料理である。
配給された小麦粉を練り、折り、焼くという作法が、そのまま持ち込まれた。
蛋餅の道筋は、もう少し曖昧で広い。
中国各地にある煎餅や、南部の粉食文化とつながっているようにも見える。
水で溶いた生地を焼くという「溶く」文化は、層を作る高度な技術を必要としない。
農作業の合間など、軽く口に入れるための食べ物として、別のルートで台湾に定着したと考えられる。
葱油餅から派生したというより、二つは最初から別の道を歩いてきたようにも思われる。
蛋餅が変わっていった過程
蛋餅は、台湾の都市化とともに姿を変えてきた。
かつては、ドロリとした粉漿をお玉で流す粉漿蛋餅が主流だった。
南部の市場や、古い店では今もその形を見ることができる。
やがて、チェーン店やコンビニが増えるにつれ、管理しやすい既製品の皮が使われるようになった。
均一な厚み、一定の焼き時間、廃棄の少なさ。
効率化の中で、液体だった蛋餅は固形のシートへと置き換えられていった。
この変化によって、見た目は葱油餅に少し近づいた。
それが二つの違いを、さらに分かりにくくしているのかもしれない。
朝に食べるものと、時間をまたぐもの
使われ方にも差があるように見える。
葱油餅は、朝食としても、午後の点心としても姿を現す。
紙袋に入れて手で持ち、かじりつくことが多い。
生地そのものの塩味とネギの香りで成立するため、必ずしもソースを必要としない。
蛋餅は、ほとんど朝だけに現れる。
昼を過ぎると、店の鉄板から姿を消す。
箸で食べられ、甘辛い醤油膏や辛味ソースをつけることが前提になっている。
皮は具材を運ぶための器のようでもある。
二つの朝のあいだで
小麦の香りを噛み締めたいとき、人は葱油餅を選ぶのかもしれない。
柔らかい包みの中で目を覚ましたいとき、人は蛋餅を手に取るのかもしれない。
二つは似ているようで、別の時間と別の歴史を背負っている。
どちらを食べるかによって、同じ朝の景色も少し違って見えることがある。